目次
腸内フローラは体にとってどんな影響を及ぼすの?
腸内フローラという言葉は、最近多くのメディアや雑誌でもよく聞く言葉となり、この腸内フローラが体の健康や美容にも大きく関係していることが分かっています。
腸内フローラは年齢やライフスタイル、ストレスなどによっても異なってきますが、この腸内フローラの状態によっては、健康に大きな影響を及ぼすことがあります。
どのような原因を引き起こしているのでしょうか?
肥満
腸内フローラは1人1人異なっていて、それぞれの腸内に600兆~1000兆個、1000種類以上の腸内細菌がいると言われています。
その中に善玉菌や悪玉菌、日和見菌がいて、善玉菌は食べ物を分解して免疫力を高める役割を持ち、悪玉菌はタンパク質の腐敗させて毒素を発生させます。
日和見菌は、腸内で優勢の方の味方をしています。

腸内では、善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7の割合が理想とされていますが、体調や加齢、食生活やストレスなどによってこの環境が崩れてしまいます。
成人の腸内環境は、「バクテロイデス門」と「フィルミクテス門」の2つの腸内細菌が優勢の状態であり、バクテロイデス門は善玉菌を好む日和見菌だと言われています。

食べ物を分解する際に排出する短鎖脂肪酸が、脂肪細胞に働きかけることで体が脂肪を取り込むことを止めて、肥満になるのを防ぐことができるのですが、フィルミクテス門の細菌は、食事から多くのエネルギー量を取り込むため、この菌が多いと肥満に繋がりやすくなります。
そのため、肥満の人は腸内細菌のフィルミクテス門が多くなり、バクテロイデス門のが少ないことが研究で分かっていて、これによって太りやすい体質が分かるだけでなく、太ることで腸内環境も悪化してしまいます。
糖尿病
糖尿病とは、本来すい臓から血糖値を下げる働きがあるインスリンが分泌されなかったり、分泌量が少ないことで血糖値が高くなる病気のことで、進行すると合併症を引き起こしたり透析が必要になります。
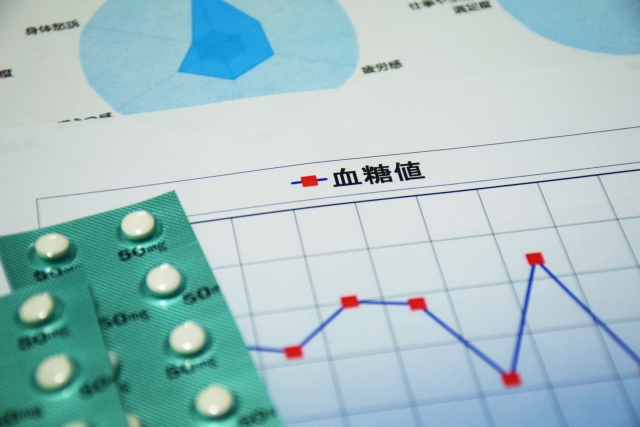
この糖尿病も腸内フローラと大きく関係があり、インスリンの分泌量には短鎖脂肪酸の減少が関係していると考えられています。
この短鎖脂肪酸が、脂肪の取り込みを抑えるのは肥満の予防になると説明しましたが、結果的に短鎖脂肪酸が減ってしまうことがインスリンの分泌量にも繋がっています。
そして、糖尿病が発症すると健康な人と同じ量のインスリンが分泌されていてもインスリンが効かなくなってしまいます。
がん
1日に3,000個以上のがん細胞が大腸で生まれているといわれていますが、そのがん細胞に対抗しているのは免疫機能です。
人間の体には免疫機能が備わっており、その重要な免疫細胞の約8割が腸内にあると言われています。

その中のクロストリジウム・アリアケ(アリアケ菌)という細菌が、がんを引き起こすと言われていますが、腸内で善玉菌が優勢であれば免疫細胞が活性化された状態であるためがん細胞を抑制できるのですが、悪玉菌が優勢の場合はアリアケ菌が排出したDCAという細胞老化物質を抑制できず、これによって老化した細胞から周囲に発がん性物質を出して、がん細胞を生み出してしまうのです。
アレルギー
アレルギーは免疫反応の一種であり、人体に害のない物質でも敵と判断して排除しようと過剰に攻撃してしまうことですが、アレルギーに対してIgE抗体ができると症状が表れます。

腸内環境が整っていなかったり、免疫機能が正常に働いていないと体が物質を排除しようとしたり、悪玉菌によって生成された有害物質が自律神経の働きを乱してしまい、アレルギーを引き起こすとも言われています。
腸内フローラの乱れによって、このような病気や疾患を引き起こしてしまう可能性があり、死に繋がってしまうこともあるので、腸内細菌を整えておくことが重要となります。
「腸内細菌は遺伝する」ってホント?
見た目や性格など、親と遺伝していると分かる部分がありますが、実は腸内細菌も同じように遺伝すると言われています。
でも、腸内細菌は生まれた時から備わっているものではなく、生まれると同時に母親の体内から受け継いで生まれてきます。

母親の胎内にいる時はほとんど無菌の状態であり、自然分娩で出産した時に産道を通ってくるため、ここで母親の持っている腸内細菌が感染して受け継がれると言われています。
また母親の腸の粘膜が遺伝することからも、同じ腸内細菌が遺伝しやすいとされています。
生まれた後に、母乳を飲んで育った赤ちゃんの腸内細菌の90%以上がビフィズス菌と言われています。
これは母乳に含まれるオリゴ糖がビフィズス菌のえさになっているため、生後6ヶ月以上母乳で育てていると腸内環境が整ってくるされています。
受け継がれるのは善玉菌だけなく、悪玉菌や日和見菌も同じため、出産前から腸内環境を整えておくと、赤ちゃんの腸内環境も良くなると言えるでしょう。

ここで出来上がった腸内環境は大人になってもそのままとなってしまうため、親子で似たような体型になったり、同じようなアレルギーを持ってしまう可能性があります。
そうなったら、親子なのであきらめるしかないと思うかもしれませんが、母親から受け継いだ腸内細菌であっても、腸内環境を整えることで改善することができます。
大人になってから腸内環境を改善させるために簡単に取り入れられる方法は、善玉菌の好むものを摂取することが良いでしょう。
特に善玉菌の中でも、ビフィズス菌が増えることが良いとされているため、ビフィズス菌を増やす栄養分となるオリゴ糖や食物繊維の摂取がおすすめです。
ビフィズス菌といっても、1種類だけでなく約50種類に分かれていて、それぞれ働きに違いがあるだけでなく必要な栄養も異なってきます。
そのため効果的な食べ物としては、ゴボウや玉ねぎに含まれるフラクトオリゴ糖、大豆や味噌に含まれる大豆オリゴ糖、善玉菌のえさとなる水溶性食物繊維等も腸内フローララ改善にもおすすめです。
腸内細菌は遺伝しますが、腸内環境を変えたい場合には、ビフィズス菌を増やすためにオリゴ糖などの糖類やタンパク質、ビタミン類やアミノ酸も重要となります。
これらを積極的に摂取して善玉菌を増やしていき、腸内環境を整えることができます。
腸内フローラに悪影響を及ぼす要因
腸はとても敏感な器官なので、ストレスや食生活の変化などの影響を受けやすくなっています。
腸内フローラを良い状態に保つためには、腸ストレスの原因をなくし、健康的な腸を育てることが大切になります。
では、腸内フローラに悪影響を及ぼす要因にはどのようなものがあるのかチェックしてみましょう。
冷え
冷えは、身体全体に悪影響を与えますが、腸にとっても良くありません。
身体が冷えると血行が悪くなり、代謝も悪くなってしまいます。
その結果、免疫力の低下にもつながります。

冷えの原因は、筋肉量が少ないこと、運動不足、夏場はクーラーに当たりすぎなどが考えられます。
女性は特に血流を促すためのポンプの役割を担っている筋肉量が少ないため、冷え性に悩む人が多く、腸のトラブルを抱えている人も多いのです。
食べすぎや偏った食生活
食べる量や食事の質は、身体作りだけではなく、腸内環境にも大きな影響を与えます。

ついつい食べ過ぎてしまう人や肉料理を食べることが多い人は、腸がストレスを感じている可能性が大きいと言えるでしょう。
腸内フローラを安定させるためには、栄養のバランスがとれた食事を心掛け、規則正しい食生活を意識することが大切です。
活性酸素やAGES(終末糖化産物)
活性酸素やAGES(終末糖化産物)は、老化の原因といわれています。
またそれらは老化の原因になるだけではなく、腸にも悪影響を与えるのです。
活性酸素やAGES(終末糖化産物)が増えると、腸内に棲みついている悪玉菌を増やすことになってしまいます。
身体と同じように腸内環境も老化していきますが、それを加速させてしまう原因にもなってしまうのです。
過度なダイエット
ダイエットをする時に、過度な食事制限をしてしまう人もいますが、それは腸内環境を悪化させる原因になります。
あまりにも過度な食事制限をしてしまうと、腸の機能が低下し、機能不全に陥ってしまう可能性もあるので注意しましょう。

その他にも食事制限をすることで必要な筋肉量も低下してしまい、将来的に更なる不調を生み出す原因になってしまう可能性もあります。
ダイエットをすること自体は悪いことではありませんが、過度な食事制限は将来的に良い結果にはならないケースがほとんどなので、長期的なスパンで計画を立てることをオススメします。
働き過ぎや睡眠不足
働き過ぎや睡眠不足は、自律神経が乱れる原因になります。
自律神経が乱れてしまうと、腸の調子も乱れてしまいます。

副交感神経が活発に働いてリラックスしている時に便意はやってくるので、逆に交感神経が活発な状態が続いてしまうのは腸にとって良くありません。
排便のタイミングを逃してしまうと、腸内フローラを悪化させる原因になってしまうので注意しましょう。
心的ストレス
緊張するとお腹が痛くなってしまったり、旅先でお腹の調子が悪くなってしまうことは、多くの人が経験したことがあるのではないでしょうか。
腸は心と深いつながりがあるので、緊張や不安を感じると腸の調子が悪くなってしまうのです。
腸内フローラを改善するためのポイント
腸内フローラは、日々のちょっとした生活の変化や不安、ストレスなどで良くも悪くもなります。
できるのであれば腸内フローラをベストな状態に保ちたいので、ここでは腸内フローラを改善するためのポイントをご紹介しましょう。
老廃物を出す
腸内に老廃物が溜まっていると、悪玉菌が増える原因になってしまいます。
腸内の老廃物を出すためには、バランスの良い食事や規則正しい食生活を心掛けることが大切になります。
コンビニのお弁当や菓子パン、加工食品、時間が経ってしまった揚げ物などを良く食べる人は、腸内に老廃物が溜まっている可能性が高いと言えるでしょう。
それらの食品には、食品添加物が多く含まれているため、老廃物を溜めやすい状態を作り出し、便秘の原因にもなってしまうのです。
定期的なファスティング等老廃物を溜め込まない生活をおすすめします。

また現代人は、食物繊維やビタミン、ミネラルといった老廃物を流してくれる栄養素の摂取が少なくなっています。
栄養をバランスよく摂取できないと腸の働きにも悪影響になってしまうため、日々の食事に気をつけましょう。
その他にも腸の働きを活発にし老廃物を排出させやすくするためには、適度な運動やストレス解消なども大切なポイントになります。
悪影響を及ぼす要因を減らす
腸内フローラに悪影響を及ぼす要因を改善することも、重要なポイントになっています。
身体を冷やさないために適度な運動、お風呂にゆっくり浸かるなどの工夫をすることで、内臓も温まるので腸内フローラに悪影響を及ぼす可能性も低くなります。

その他にも、ストレスを抱えない為に働き過ぎや睡眠不足にならないように心掛けたり、心的なストレスをできるだけ抱え込まないようにすることも大切です。
悪影響を及ぼす要因を少しでも減らすことができれば、腸内フローラも改善されていくと考えられます。
呼吸や姿勢を意識する
腸内フローラを改善するために、呼吸や姿勢を意識して腸に良い運動を行うことを取り組む事で、健康な状態を保つ事ができます。
実際良い状態を保つためには、やり方として、
5秒で鼻から吸って、10秒かけて口からゆっくり吐く呼吸を寝る前に10回程度行うというものです。

この呼吸法を実践するときに、お腹が動くように意識する腹式呼吸を行うことで、腸の周辺にある筋肉が刺激され、腸の働きも活発になっていきます。
また腹式呼吸を実践すると、自律神経を整える効果もあるため、心身ともに落ち着くことができるでしょう。
腸内フローラを改善させるためには、腸内フローラが身体にどのような影響を与えるのかを知り、悪影響を与える要因や改善方法を知ることが大切になります。
腸内フローラは、腸だけではなく体質や様々な病気の原因にもなっていることを知ると、改善する努力もできるはずです。
今回は、腸内フローラを改善させるために必要な知識をピックアップして紹介しました。
悪影響を与える要因に当てはまるものがあった人や今後気をつけたいと思った人はぜひ参考にしてみてください。
腸内フローラを整えることで、心身ともに健康な生活を送るきっかけになるはずです。













